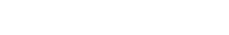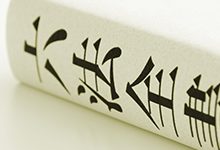有給休暇
 みなさん、「有給休暇」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
みなさん、「有給休暇」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「有給休暇」とは、正式な名称を「年次有給休暇」といい、その制度の趣旨は、労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために、労働者に対し、休日のほかに毎年一定日数の休暇を有給で保障するというものです。
年次有給休暇の権利の中身は、一般的に、労働基準法上の要件(①6ヶ月間の継続勤務 ②全労働日の8割以上出勤)が充足されることによって法律上当然に発生するとされる「年休権」と、発生した年休を取得する時季を指定する「時季指定権」から成るとされています。
では、有給休暇の具体的な日数(これを「付与日数」と言います。)はどのようにして決まるのでしょうか。この点についても、労働基準法で定められており、雇い入れの日から起算した勤続期間が6 ヶ月の場合、付与される休暇の日数は、10 日間です。1 年6 ヶ月になると、11 日間与えられ、2年6 ヶ月で12 日間、3年6 ヶ月で14 日間、4年6 ヶ月で16 日間、5年6 ヶ月で18 日間、6年6 ヶ月で20 日間、それ以上は頭打ちとなります。つまり、7年6 ヶ月以上を勤務すれば、法律上は最大で40 日間の有給休暇を取得することができるのです。
有給休暇は法律上認められた権利です。ですから、例えば会社によっては、「うちには有給の制度なんて無いよ」と言われることもあるようですが、これは間違いです。仮に、何ら正当な理由無く、年次有給休暇の権利を侵害すると、労基法119条1号で、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に科される可能性があります。
権利として認められているのですから、これを行使しないことはありません。
時季変更権
さきほど、有給休暇は権利として認められているとご説明しました。もっとも、会社側としては、勤めている人が一斉に有給休暇を取得すれば、働く人が誰もいなくなって、会社の経営が立ち行かなくなるかもしれません。そこで、労働基準法39 条5 項により「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と定められ、使用者が時季の変更を求めることができるとされています。「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるかについては、事業所の規模、業務内容、担当する職務の内容、性質、繁忙期か、代わりの人を確保できるか、同じ時期に休暇を取る他の社員の人数や、これまでの休暇の取り方の慣行を考慮要素として、個別、具体的に客観的に判断されます。
時季変更権の判断要素に関する判例
最後に、以下の判例(最高裁昭和62年7月10日第二小法廷判決民集41巻5号1229頁(弘前電報電話局事件))を紹介しておきましょう。これは、時季変更権行使の判断要素である「代替要員確保の難易」について判断した判例で、利用目的についても判示しています。すなわち、判例は、「労基法三九条三項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。
従って、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。
そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところである(前記各最高裁判決参照)から、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」としました。
もし、このコラムを読んでいる皆さんの中に、会社が有給休暇を認めてくれないといった方がいらっしゃいましたら、いつでもご相談ください。
当所では初回相談料を無料とさせていただいておりますので、いつでも、お気軽にご相談いただければと思います。